2025年3月31日 作成
後期高齢者医療制度の概要
後期高齢者医療制度は平成20年4月から始まった75歳以上の人や65歳以上で一定の障害のある人を対象とした医療保険制度です。
後期高齢者医療制度に加入すると、これまでの国民健康保険や社会保険(健康保険や共済保険)を脱退することになります。
後期高齢者医療制度においては、加入する被保険者一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
また、制度の運営(保険者)は静岡県全市町が加入する静岡県後期高齢者医療広域連合が行います。
詳細につきましては、静岡県後期高齢者医療広域連合のHPをご覧ください。
広域連合と町の役割
後期高齢者医療制度では、高齢化の進展や老人医療費の増大により、保険財政の安定化を図るため都道府県単位で全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が設立され、後期高齢者医療制度の運営を担うことになりました。
〈広域連合〉が行う主な業務
・被保険者の資格管理 ・資格確認書等の交付決定 ・保険料率の決定
・保険料の賦課、減免等の決定 ・医療給付の支給、不支給の決定 ・一部負担金の減免や減額の決定 など
〈町〉が行う主な業務
・被保険者の資格管理に関する申請受付 ・資格確認書等の引渡し ・保険料の徴収
・医療給付、一部負担金に関する申請受付 ・健康診査の実施、人間ドック費用の助成 など
病院等の医療機関にかかるとき
医療機関の窓口で「後期高齢者医療被保険者証」「後期高齢者医療資格確認書」「マイナ保険証」のいずれかを提示してください。医療機関等で支払う自己負担割合は、所得の区分に応じて1割、2割または3割になります。
自己負担割合
| 所得の区分 |
自己負担割合 |
所得の基準額 |
| 現役並み3 |
3割 |
住民税の課税所得が690万円以上ある被保険者がいる世帯 |
| 現役並み2 |
住民税の課税所得が380万円以上ある被保険者がいる世帯 |
| 現役並み1 |
住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者がいる世帯 |
| 一般2 |
2割 |
〈世帯内の被保険者が1名の場合〉住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者 |
| 〈世帯内の被保険者が2名以上いる場合〉住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員 |
| 一般1 |
1割 |
他の所得区分に該当しない世帯 |
| 低所得者2 |
同じ世帯の人全員に住民税が課税されていない世帯 |
| 低所得者1 |
同じ世帯の人全員に住民税が課税されていない世帯のうち、全員の所得が一定の基準に満たない世帯 |
※ただし、現役並み所得者でも生年月日が昭和20年1月2日以降であり、かつ世帯の被保険者の旧ただし書所得(総所得金額等から43万円を引いた金額)の合計額が210万円以下である場合には、1割または2割負担になります。
※また、現役並み所得者でも次のいずれかに当てはまる人は、申請することにより、1割または2割負担になります。
同じ世帯の被保険者が2人以上であり、収入合計額が520万円未満
同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円未満
同じ世帯の被保険者が1人のみであり、収入合計額が383万円以上であるが、同じ世帯に70歳から75歳未満の人がおり、その人との収入合計額が520万円未満
後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
2022年(令和4年)10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合が3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
→上記の制度は、令和7年9月30日で終了しました。ご承知おきください。
後期高齢者医療制度の届出(手続き)について
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者医療制度の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う自己負担額を除いた分について、約5割を公費で国・県・市が負担、約4割を現役世代(75歳未満の方)が負担し、残りの約1割を被保険者が全員で保険料として負担しています。
保険料の額
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」とそれぞれの所得に応じて負担する「所得割額」の合計となり、個人単位で計算し、県下同一基準で算定されます。均等割額と所得割額は2年ごとに見直されます。
令和6年度から令和7年度の保険料率
- 均等割額…年間47,000円
- 所得割額…基礎控除(43万円)後の総所得金額等×所得割率(9.49%)
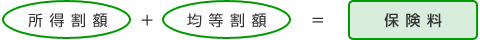
均等割額+所得割額=年間の保険料額80万円を限度とする
保険料の軽減
- 均等割額の軽減 世帯の所得にあわせて、下のとおり軽減されます。
| 世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計 |
軽減の割合 |
| 43万円+(給与所得者等の数※2 -1)×10万円 以下のとき |
7割 |
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+29.5万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
5割 |
| 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+54.5万円×世帯の被保険者数 以下のとき |
2割 |
※均等割軽減の判定時には、保険料がかかる年の1月1日現在で65歳以上の人の公的年金等に係る所得からは、さらに15万円を控除します。
※給与所得者等の数とは、一定の給与所得(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の数です。
-
健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割額が5割軽減されます。
-
災害に見舞われた場合や失業・事業の不振等により収入が著しく減少した場合など、保険料の納付が著しく困難になった際には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
保険料の納め方について
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。納め方は、【特別徴収】年金からの天引きと【普通徴収】納付書や口座振替で納める方法があります。
《特別徴収》保険料を年金から徴収される方
年6回の年金支給時に、年金の受給額から保険料額があらかじめ差し引かれます。
ただし、次のいずれかに該当する方は、納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。
・特別徴収の対象となる年金の年額が18万円未満の方
・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の2分の1を超える方
・介護保険料が特別徴収でない方
・年度途中で75歳になった方
・年金天引きから口座振替へ変更の申し出をした方 など
《普通徴収》納付書や口座振替で納める方
毎年、8月に当年度の保険料が決定し、通知いたします。町から送付される納付書により、納期限日までに納めてください。口座振替の方は、納期限日に口座から自動的に振り替えとなります。
普通徴収の納期 ※ 納期が末日の場合、翌営業日が納期限日になります。
| 期別 |
納期 |
期別 |
納期 |
| 第1期 |
8月末日 |
第5期 |
12月末日 |
| 第2期 |
9月末日 |
第6期 |
1月末日 |
| 第3期 |
10月末日 |
第7期 |
2月末日 |
| 第4期 |
11月末日 |
第8期 |
3月末日 |
<注意>
新たに後期高齢者医療制度に加入された方の保険料の決定時期は、お誕生月または加入された月の翌々月になります。
※お誕生月が2月の方は、4月に前年度分の保険料額が決定し、4月末日が納期限の納付書が届きます。
※お誕生月が3月の方は、5月に前年度分の保険料額が決定し、5月末日が納期限の納付書が届きます。
※年金からの天引きである方でも、口座振替を選択することで、年金からの天引きを中止することができます。ご希望の方は担当課までお問い合わせください。ただし、後期高齢者医療保険料に滞納がある場合は、口座振替を選択できないことがあります。
納付済額のお知らせ
毎年、1月中に前年の1月1日から12月31日までに納めていただいた後期高齢者医療保険料について、納付済額のお知らせ(確定申告用)を発送しています。
確定申告等で社会保険料控除として申告される方は、参考にしてください。
※年末調整に利用するなど、1月の発送より前に必要な場合は、担当課へお問い合わせください。